はじめに
大学生は通常、世界に関する新しい知識、確信、あるいは真実を獲得することを目指して大学教育を受けることにしている。 最近の研究では、学生が心や世界とのつながりに関する知識を得ようとすると、すぐに哲学的な心身問題、あるいは一般に「物質二元論」あるいは「デカルト的二元論」と呼ばれるものに直面することが明らかになった(Fahrenberg and Cheetham, 2000)。 非物質的な心と物質的な身体との間の厳密な存在論的・認識論的差異を主張する心理学の学生は、このデカルト的物質二元論をより詳細に批判的に検討することができず、知識や事実の丸暗記や表面だけの学習をより重視する。このことは、ライアン(1984)が理解や深い学習に伴う解釈と理解のプロセスよりも効果がないことを実証している。 つまり、二元論的な認識論は、心理学の授業において、知識の応用力を弱め、成績の低下を招くのである(Ryan, 1984; Lonka and Lindblom-Ylanne, 1996)。 これはまた、無批判な科学的二元論的信念を将来の科学、準医療、医学の専門職に暗黙のうちに伝達する危険性もはらんでいる(Demertzi et al.) そこで、この論文では、教室におけるこの暗黙の二元論を探求するために、教員と学生が同様に受け入れることができる教育的ツールを提供する。第一に、ルネ・デカルトの二元論的哲学ではなく、マルティン・ハイデガーの全体論的哲学に基づく、学習と教育のための代替的な哲学的基盤または認識論を提示する。 第二に、「ピノキオ」や「ゴム手」のような、心の身体表現を操作する簡単な神経科学の錯視を通して、この代替的な認識論の視点を実際に説明することです。 そうすることで、講師は、これらの議論や演習を行う前に学生が持っていた暗黙の二元論的前提をより明確にし、学生がそれについてより批判的に検討し考えることができるようにすることができるのです。 このように、異なる認識論と実践的なデモンストレーションによって、講師は教室で二元論的な信念を暴露したり挑戦したりし、心と体がどのように世界と関係しているかを考える別の方法を示すことによって、学生の中に深い学習や理解を促すことができるのです。
啓蒙主義以来(他の形ではプラトン以来)西洋哲学を悩ませてきた形而上学的問題を偽ることは不可能ですが、この記事の目的はデカルトの二元論自体を攻撃することでも、二元論的思考に反するまたは代替するすべての哲学的観点を検証することでもありません。 これは複雑で膨大な哲学的・科学的課題であり、この短い記事の範囲外である。 つまり、心身二元論を支える表面的な認識論的前提とは異なる、心と身体がどのように相互接続し、重なり合い、存在するのかをより全体的に考え、理解する方法である。 そうすることで、形而上学的な二元論に対抗したり反証したりするのではなく、学生が自分たちの世界や、深い学びと理解に適した別の方法でそれを開示する他の哲学や実践について批判的に考えるための新しい空間を開くことを目的としているのである。 708>
カルテスの二元論
ルネ・デカルト(1596-1650)は、17世紀のフランスの数学者、哲学者、科学者です。 分析幾何学の創始者であり、真理、確実性、精神と身体の存在論的理解、認識論的結びつきを革新的に再定義したことから、現在では近代哲学の父と呼ばれることが多くなっている。 デカルト以前は、心の構成は、カトリックの正統派が主張するように、「魂」が感覚刺激を配列して思考を形成することに起因するとされていた。 心と身体は一人の人間の中で全体として融合しており、魂に関わる真理や確信は神によってアプリオリに決定されていた。 708>
人間の思考と存在のすべてを単に神に帰するのではなく、デカルトの合理主義は、真理と確信のための革命的な新しい基盤、すなわち主体の理性と思考の心、あるいは主観性の「私」を提起した(デカルト、1998年)。 この新しい自己確証の合理性は、根本的な懐疑、すなわち疑いの能力に基づいている。 デカルト的な疑いの呪縛のもとでは、身体的な視覚、味覚、触覚などを通じて物質世界から発せられるあらゆる経験的刺激が、夢と同様に、これらの身体的感覚が本物であると確信できないため、常に心を惑わせる可能性があるのだ。 「デカルトは、「私は、真理の源である最高に善良な神ではなく、むしろ、私を欺くことに全力を注いだ、最高に強力で巧妙な悪の天才を想定する」と書いています。 (デカルト, 1998, p.62) 「空気、大地、色、形、音」、あるいは我々の感覚的身体と実体的物質世界を構成するレス・エクステンサが実際に存在することを確かめる方法がない以上、デカルトはただ一つのどうしようもない確実性と真実だけが残ると主張したのである。 「私は、考えるためには、存在することが必要であることをはっきりと理解している」(p.18)。 疑うこと、それはやはり考えることであり、考えることは存在すること、あるいは存在することである。 それゆえ、デカルトの有名な格言は、今日に至るまで二元論的認識論の根幹をなしているのである。 「我思う、ゆえに我あり」(cogito ergo sum)(p. 18)。 この格言によれば、私たちは自分の考える心が、感覚を持つ物質や身体とは別に存在すると確信することができる。 「目で見たつもりが、実は心の中にある判断能力だけで把握していた」。 (p. 68). 私の身体が水と氷という異なる物質だと言っているものを、私の心が同じ物質だと判断したのである。 デカルトの合理主義・二元論の後進たちは、魂(心)が脳の松果体を通じて身体の機械的な働きの「生命的な精神」に出会い、影響を与えることができるというデカルトの古めかしい考えを捨てたが、彼が提起した思考/物質、主観/客観、心/身体間の二元的認識論は、今日まで、西洋科学、哲学、科学・文化論に暗黙のうちに根付き続けているのである。
たとえば、講師は、二元論的な認識論を説明する(そして定着させる危険がある)文化的な例として、『マトリックス』(1999)や『インセプション』(2010)などの最近のハリウッド映画を容易に参照できます。デカルトの「悪い天才」のように、これらの映画は、感覚的な身体刺激から得られる真実や確信が確かに夢のようだったり誤解を招くかもしれないが、考える自己とその理性によって訂正したり克服したりする可能性を強調しています。 ここで、心は、刺激が信頼できない身体の牢獄から、しっかりと区別され、分離され、解放される必要があるものとして描かれているのである。 実際、最近の研究では、二元論的な考え方は、科学、医療、パラメディカルな環境において、学問的背景や訓練に関係なく、学生の教育を通じて保持されることが証明されている。 Demertziら(2009)は、スコットランドのエジンバラ大学の学生、ベルギーのレージュ大学の医療従事者と一般市民をサンプルに、二元論的信念の有無を調査した。 調査対象となった学部学生の大多数は「心と脳は別物である」という意見に同意し、リエージュの調査参加者の半数弱はこの意見に同意していました(Demertzi et al.、2009)。 興味深いことに、調査対象となった医療従事者のほぼ半数も、この二元論的な発言に同意している。 これらの結果は、神経科学研究、特に機能的磁気共鳴画像法(fMRI)を用いた研究が、神経活動が心理現象に関与していること(Greeneら、2001;FarrerとFrith、2002)、したがって脳が心の起源であることを示唆し続けているにもかかわらず、社会全体に二元論信念が存在し続けていることを強調するものである。 しかし、二元論を信じるかどうかは、科学的研究によって提供される証拠の強さを知覚するかどうかにも依存する。 心理現象を記述した弱い神経科学的証拠にさらされたとき、被験者は魂の存在を信じる傾向が強まる。 逆に、神経科学的根拠が強いと、被験者は魂への信仰を低下させる傾向がある(Preston et al.、2013)。 したがって、神経科学や心理学の教室では、現在の研究を正確に説明することが重要であり、それによって、心、脳、身体の関係を問題化し、学生や講師がより批判的に探求することができるようになる。 また、医学的に説明のつかない症状の原因を心理的ではなく身体的なものに求めようとする人もおり(Geist et al.、2008)、心と物質というデカルト的な二項対立が強まっている。 実際、「魂」は身体の死や破壊を乗り越えて生存するという信念は、科学界に広く残っており、二元論が心理学自身の「神経科学的思考」にまで影響を与え、物質の脳が心を生み出し、しかし心とは根本的に分離したままであると暗示している(Demertzi et al.、2009)。 しかし、二元論的な思考パターンは、実際に日常生活に害を及ぼす可能性があるのだろうか。 最近、研究者たちは、プライミング手順を使って「二元論者」または「物理主義者」のいずれかの信念を誘発し、二元論者の条件では、被験者の態度や行動がより健全でないことを発見しました (Forstmann et al., 2012)。 デカルトとハイデガー
もし大学での訓練や教育が依然として二元論の前提を保持する危険をはらんでいるなら、教官はどのようにして学生の間で二元論的認識論のより批判的で有意義な分析を奨励できるでしょうか。 心身問題や二元論的認識論の微妙な前提を検証する場合、哲学と科学は連携して取り組むことができる。 西洋哲学の広大なキャンバスの中から一例を挙げると、マルティン・ハイデガーの基本的な著作を検証してみましょう。これは、指導者が学生に異なる、しかし同様に強力な認識論的視点と世界の理解を提供する方法の例となりえます。 708>
哲学的には、心と物質の間の存在論的分離というデカルト二元論の主張は、マルティン・ハイデガーの『存在と時間』とその「世界における存在」(ハイデガー、1962年)という革命的概念の出版によって根本的に損なわれた。 ハイデガーは、二元論的認識論の二項対立とは逆に、私たちの近代的で自然化された主観性、「私」、コギト、あるいは心といった概念は、二元論が想定するように、決して物、物質、あるいは世界から分離・離脱できないことを主張したのである。 デカルトにとって、ある主体がハンマー、ドアノブ、鉛筆などの日常的な物を見て、認識し、使用するとき、彼らの考える心は、物質と身体の世界との存在論的溝を越え、これらの物質的物質の感覚刺激と経験的特性を獲得し、心の中で計算し、推論し、そして作動させて、その合理的使用を行う(ハイデガー、1962、p.128)。 しかし、ハイデガーの根本的な洞察は、これらの「対象」のそれぞれが「主体」にとって意味をなすのは、いかなる精神的合理化、離散的思考、感覚的特性の組み合わせによってももたらされないということであった。 むしろ、事物は、事前反射的、学習的、日常的な文脈上の実践や使用を通じてのみ、人間である私たちに意味を持ち、あるいは開示されるのである。 つまり、現代において、ハンマーのような単純なものが、木に釘を打つことができるものとして認識されるのは、その人がすでに文化的、言語的、言説的実践を共有する世界の中で社会化され、この「ハンマーというもの」がこのように特定の方法で使われることを教わった後なのである。 したがって、木の棒や金属の塊は、共有された世界に取り込まれることによって、それを使うべきものとして理解できるようにする社会的・文化的文脈と状況が開示された後にのみ、ハンマーとして私たちに開示されるのである。 「このような実体がダーザインに「会う」ことができるのは、それが自らの意志で世界の中に自らを示すことができる限りにおいてのみである」(ハイデガー、1962、p.84)。 ここで重要なのは、指導者がハイデガーの哲学を道具として使い、学生の暗黙の「世界の中にいること」が、彼らがかつて当然と考えたり、想定したりしていた二元論の形而上学的前提をいかに含み、下支えしているかを示すことができるということである
さらに深く調べてみると、人が実際に釘打ちをし、ドアノブを回し、玄関を通って歩き、鉛筆を使って心理学のメモなどを書きとめる過程にあるとき。 デカルトの心身二元論を支えていた存在論的分離が崩壊する。 なぜだろうか。 ハイデガーによれば、これらの「物」は、歴史的、社会的、文化的な無数の複雑で相互依存的なネットワーク化された文脈の中に取り込まれ、それらが組み合わさって「物」に自然化された意味、意義、使用を与えるので、それぞれが理解可能になり理解できるようになるのである。 私たちはハンマーを釘を打つための道具として文脈化しているが、古代ギリシャ人や他の惑星から来た宇宙人は、この「物」を私たちにとって意味深く、理解しやすいものにする社会的、文化的、心理的文脈を欠いているだろう。板、釘、のこぎり、ねじ、構造物、本棚、はしご、ペンキなどは、歴史的、文化的に私たちにとってユニークでありながら、日常の社会的使用を通して獲得し暗黙化する「装備的全体性」(ハイデガー、1962)を形成して結合する。 これらは、私たちの世界が理解できるようにするあらゆるものと関連し、ネットワーク化された無数のものであり、その背景となる関連性や文脈が、特定の方法で使用するために、それを理解できるものにする。 このように考えると、いくら合理的に考えても、二元論的な文脈では、ハンマーのような単純なものが実際に何であるかを知ることはできない。 学生が初めてハンマーを見て、その使い方を合理的に説明することはできない。 その代わり、”エージェンシーを可能にするのは、何か根本的な基盤や精神的な物質ではなく、むしろ、共有された意味のある世界の実践を背景に、私たちの人生の物語が展開される方法である。”と。 (Guignon, 2006, p. 9) したがって、ハイデガーの有名な口述「世界における存在」は、主体と客体、心と身体などの間の想定される溝や二元論を排除する(Heidegger, 1962). この世界では、理解、コミュニケーション、ナビゲート、実践、そして絡み合った文脈と意味の世界における自らの「存在」について、特殊で事前反射的な方法が刷り込まれているのである。 繰り返しになりますが、ここで重要なのは、上で検討したデカルト的二元論的認識論のような近代的、日常的、暗黙の文化的実践が、私たち自身の特定の歴史的文脈において、心と体を二つの別々の実体として明らかにしたり開示したりするまで、心と体は本来異なる物質ではない、ということです。 そこで、心理学入門の授業では、この哲学を教育的ツールとして活用するために、上記のハイデガー的事例を講義し、その後、教室でのディスカッションやグループ活動を通じて、学生がこの概念とこの相反する認識論的視点を理解しているかどうかを判断することができる。 例えば、”デカルト的二元論を前提とした最近の映画やテレビシリーズの例を挙げ、ハイデガーの立場と対比させる “などである。 簡単な例として表1を参照。 したがって、以下で検討するように、空間における私たちの身体の存在に関する常識的な(誤った)理解を問題化する心理的錯覚は、世界における私たちの身体の継続的な位置づけが、しばしば忘れられたり当然とされたりすることを示すのに役立つだろう。
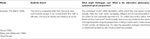
Table 1. メディアにおける二元論的なテーマについて議論し、批判するための教室でのエクササイズ。
Body Representation and Body Schema
個人と外界との間のあらゆる物理的相互作用、たとえばハンマーを使って釘を打つ、教室で鉛筆を使う、道を歩いているときに鉄塔を避ける、などが起こるためには、心が空間における自分の身体の位置についての概念を持っていなければならない。 心は世界の中に位置していなければならない。 プロプリオセプターは筋肉や関節にある受容体で、筋肉の伸縮や関節の角度に関する情報を視床に伝え、最終的には大脳皮質の体性感覚野に伝達します。 心の中の身体のスキーマは、固有感覚と他の感覚、すなわち視覚と運動系からのフィードバックを組み込んで、人間(そしておそらく他のほとんどの動物)がその外部空間における身体の位置を精神的にモデル化することを可能にしているのです。 ボディスキーマは、さまざまな知覚入力を関連付け、不足している情報を計算して再構成し、矛盾を検出して解決することで、身体の配置を常に意識化する役割を担っている(Graziano and Botvinick, 2002)。 教室では、心と体が同じものであるかもしれないことを明確に示すことは困難な作業となることがある。 しかし、この目的のために、心の身体スキーマを変化させる簡単な知覚のデモンストレーションがいくつかある。 このように、身体の感覚系への入力を変化させることで、心は混乱し、身体に起こっていることについて錯覚的な結論を出すことができる。 もし主観的な経験が、私たちの感覚物質や身体とは異なる存在である心によってもたらされるとしたら、感覚の変化による錯覚は心に影響を与えるだろうか。 デカルトのような相互作用型二元論者によれば、心と身体は因果関係にあり、互いにコミュニケーションをとることができ、この魂と身体の相互作用は松果体を通して行われるとされている。 しかし、もし心が、部分的に身体の感覚システム(その接続は松果体とは無関係)の影響を受けている脳の神経回路の活動によって生成されているとすれば、脳への入力が混乱することによって、心の知覚が変化し、錯覚する可能性がある。 実際、このような考えに基づいて、「幻肢痛」の治療法を開発した科学者もいる。 幻肢痛とは、切断された手足がまだ痛むという症状です。 教育関係者は、学生にこの興味深い状態を教え、この状態の治療法として「ミラーボックス」について説明することをお勧めします(McGeoch and Ramachandran, 2012; Youtube link1もご覧ください)。 以下は、教室でできる簡単だが示唆に富む2つのイリュージョンの説明である。 これらのデモンストレーションは、生徒の集中力を維持し、心身の二元性について議論するために異なるモダリティを使用するための顕著なメカニズムとなり得る。
ピノキオの錯視
1940年代のウォルト・ディズニー映画の中で、ピノキオは木でできた架空の人形で、彼が嘘をつくと鼻が伸びることで知られています。 上腕二頭筋腱を振動させることにより、脳に体性感覚を送り、鼻が伸びる感覚を呼び起こすことができるため、「ピノキオ錯視」と呼ばれている(Lackner, 1988)。 この単純な錯視は、被験者に目を閉じてもらい、その腕の上腕二頭筋腱を振動させながら指で鼻を触らせることで生じる(図1参照)。 一部の被験者に生じる幻視感覚は、鼻が伸びることである(Burrack and Brugger, 2005)。 上腕二頭筋腱の振動は、筋棘をトリガーとして、腕の伸展(肘関節角度の増加;DiZio and Lackner, 2002)を知らせる固有受容入力を脳に送る。 脳は鼻と指先の両方から触れているという触覚入力も得ているため、これらの刺激が脳内で組み合わされ、鼻が伸びている/顔から遠ざかっていると誤って結論付けてしまうのです。 なお、最適な効果を得るためには、利き腕を約100Hzの振動数で使用する必要があり(Burrack and Brugger, 2005)、したがって、基本的なハンドマッサージャーは錯覚を起こさないかもしれません。

図1. ピノキオ錯視。 (A)被験者は利き腕を伸ばし、上腕二頭筋腱に振動を与える。 このとき、腕の中心部に振動を加えることが重要である(矢印)。 (B) 被験者は腕を曲げ、目を閉じ、人差し指を鼻に当てます。 708>
ゴム手錯視
もう一つの錯視は、一般に「ゴム手錯視」(Botvinick and Cohen, 1998)と呼ばれ、外部の物体(一般にはゴム手)が体の一部であると感じられるように心を騙します(図2参照、2も参照)。 この錯視では、参加者はテーブルの上に置かれたゴムの手に視界を向け、対応する左右の手は視界の外に置かれる。 錯視を行う人は、絵筆でゴム手を本物の手と同じように触ります。 数分間、指、指関節、手にペンキを塗っていると、ほとんどの参加者はゴム手が自分の体の一部のように感じられるようになります。 これは、目の光受容器と皮膚の機械受容器と固有受容器が受け取る外部刺激からの相反する入力によるものです。 この相反する入力は、視床から体性感覚野に伝わり、さらに大脳皮質の連合野で、「身体の外側にある物体は身体の一部でなければならない」という誤った最終判断を下してしまうのです。 この意味で、脳は身体のスキーマの心的イメージを、ゴム手を取り込むように変化させたのです。 研究者たちは、被験者に追試をしてもらうことで、これが空間の中で手がどこに位置しているかという身体の知覚の変化であることを証明しました。 左手にゴム手の錯視を施した後、被験者に目を閉じて、左手があると信じている場所に右手(テーブルの下)を並べるように指示しました。 その結果、被験者が左手があると思った場所は、錯視されたゴム手の方向に大きくずれており、この歪みの強さはゴム手の錯視そのものの効果と相関していることが分かりました(Botvinick and Cohen, 1998)。 絵筆と人の手の模型を用いた研究報告もあるが(Botvinick and Cohen, 1998)、ゴム手の模型と絵筆がない場合は手袋と指先による手の触覚刺激でもよい
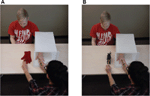
Figure 2. ゴム手錯視。 (A)参加者は左手を囲いの中に伸ばして、自分の手を見ることができないようにする。 参加者は、囲いの中で自分の手と同じ向きにあるゴムの手(手袋)を見つめます。 錯視を行う人は、両方の絵筆を使って、参加者とゴムの手に同じように触れます。 錯視は通常1〜2分で効果が現れる。 (B)錯視に非常に弱い被験者には、ゴム手があった場所に別の物体を置くこともある。 この場合、錯視を起こす人は、恐竜と手を同じように「塗る」ことになります。 708>
まとめ
この展望記事では、デカルトの二元論を支える認識論的前提を、哲学的および科学的根拠に基づいて探求する方法を講師が概説してきました。 例えば、ハンマーのような単純なものを使用する際に必要とされる暗黙の理解は、身体的な感覚データや刺激から離れた合理化ではなく、その使用を理解可能かつ正常なものにする文化的実践に由来しているのです。 心理学的なラバーバンドやピノキオ・イリュージョンは、デカルトが強調した心と体の二元論を越えて、身体と心が共有する世界に入り込んでいるという基本的な洞察を補強しているが、理性が真実を理解するための優れた先験的尺度であるわけではないことを理解した上で、である。 哲学、形而上学、科学でさえも、理性的な心それ自体から発せられることのない世界観の共有によって支えられている。 例えば、触覚や振動で身体を刺激すると、その感覚入力は、身体が外部空間のどこにあるかという脳の心的スキーマに組み込まれ、ここに述べたような錯覚を伴う。そして、これは心によって誤って幻想的な結論(鼻が生えているとか、ゴム手が自分の身体の一部であるなど)として解釈されるのである。 このように、身体、自己、世界に関する心の合理的な前提が問題化される。 そうすることで、これらの単純なイリュージョンを単独で、あるいは異なる哲学的視点とともに提示し、二元論的前提についての批判的思考の向上を促すことで、学生を教育するための教育的ツールとすることができる」
利益相反声明
著者らは、この研究が潜在的利益相反として解釈されるいかなる商業または金銭的関係からも解放されて行われたと宣言する。
謝辞
本書は、自然科学・工学研究会議(NSERC)のTH(04843)に対するディスカバリーグラントおよびMacEwanリサーチオフィス、ロンドン大学経済・政治学部の国際関係学科によって支援されたものである。 また、図1と図2の錯視を実演してくれたAdrian JohnsonとAdam Morrillに感謝する。
脚注
- ^ http://www.ted.com/talks/vilayanur_ramachandran_on_your_mind?language=en
- ^ https://www.youtube.com/watch?v=TCQbygjG0RU
デカルト、R. (1998). 方法論講義と第一哲学の瞑想』第4版. Indianapolis, IN: Hackett Publishing Company, Inc.
Google Scholar
Heidegger, M. (1962)。 存在と時間. New York: Harper and Row Publishers.
Google Scholar
Lackner, J. R. (1988). 体型と向きの知覚表現に対するいくつかの自己受容の影響。 脳 111, 281-297. doi: 10.1093/brain/111.2.281
PubMed Abstract | CrossRef Full Text | Google Scholar
Stone, J. (2006). 機能的弱点。 博士論文、エジンバラ大学、英国.
Google Scholar
.